冬の突然の降雪や積雪時に備えて、布製タイヤチェーンを検討している方も多いでしょう。しかし、「タイヤ チェーン 布 何回使えるのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。布製タイヤチェーンは、金属チェーンや非金属チェーンと異なり、使用回数に制限があるため、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では、布製タイヤチェーンの使用回数の目安や、代表的な製品であるオートソックは何回使えるのか?寿命の目安について詳しく解説します。また、布チェーンはノーマルタイヤでも使えるのか?という疑問にも答え、適切な使用シーンについて説明します。
一方で、布製タイヤチェーンにはメリットだけでなくデメリットも存在します。布製タイヤチェーンのデメリットと注意点を押さえ、誤った使い方をしないようにすることが重要です。また、すべての環境で使えるわけではなく、オートソックが使えないケースとは?というポイントも理解しておく必要があります。
さらに、布製タイヤチェーンをできるだけ長持ちさせるためには、適切な使用方法や保管が欠かせません。長持ちさせるための使い方とメンテナンス方法を知っておけば、無駄な買い替えを防ぎ、コストを抑えることもできます。
これから布製タイヤチェーンを購入しようと考えている方、すでに持っているけれど使用回数や寿命が気になっている方は、ぜひ最後まで読んで、安全な冬のドライブに役立ててください。

何回使えるかが一番気になるところだよねー
- 布製タイヤチェーンの使用回数の目安や寿命の影響要因
- オートソックを含む布製チェーンの耐久性と適切な使い方
- 布製タイヤチェーンのメリット・デメリットと注意点
- 長持ちさせるためのメンテナンス方法と保管のポイント
布製タイヤチェーンは何回使える?耐久性と寿命を解説


- 布製タイヤチェーンとは?基本情報と特徴
- 布製タイヤチェーンの使用回数の目安
- オートソックは何回使える?寿命の目安
- 布チェーンはノーマルタイヤでも使えるのか?
- タイヤチェーンの耐久性はどのくらい?
- 布製タイヤチェーンのデメリットと注意点
布製タイヤチェーンとは?基本情報と特徴


布製タイヤチェーンとは、ポリエステルなどの特殊な布素材を使用した滑り止めアイテムのことです。従来の金属チェーンや非金属チェーンとは異なり、軽量で取り付けやすい点が特徴です。特に、冬の突然の降雪や急な積雪時に、簡単に装着できるため、初心者や力の弱い方でも扱いやすいとされています。
布製タイヤチェーンの最大の特徴は、その素材の特性による「雪道での高いグリップ力」です。布が雪とタイヤの間に適度な摩擦を生み出し、スリップを防ぎます。これにより、アイスバーンや圧雪路でも一定の制動力が得られるのです。ただし、チェーンと聞くと頑丈なイメージを持つかもしれませんが、布製のものは耐久性に限界があります。あくまで「一時的な使用」に適した製品であり、長期間の使用には向きません。
また、布製タイヤチェーンは、金属チェーンや非金属チェーンと比べて振動や走行音が少ないのもメリットです。金属チェーンの場合、走行中に「ガタガタ」とした振動があり、乗り心地に影響を与えることがあります。しかし、布製タイヤチェーンはその点で快適な走行が可能です。さらに、金属チェーンのように路面を傷つける心配がないため、一部の道路では使用が許可されていることもあります。
一方で、デメリットもあります。例えば、乾燥した舗装路では摩耗が早く進むため、雪がない場所での走行には適していません。また、再利用回数にも限界があり、使い続けるとグリップ力が低下してしまいます。そのため、緊急時の対策として車に積んでおくのは良いですが、冬場の常用には向いていないのです。
このように、布製タイヤチェーンは「簡単に装着できる」「振動が少なく快適」「金属チェーンより軽い」という利点を持ちながらも、「耐久性に制限がある」「乾燥路面ではすぐに摩耗する」という欠点もあります。したがって、適切なシーンで使用することが大切です。
布製タイヤチェーンの使用回数の目安


布製タイヤチェーンの使用回数には明確な基準があるわけではありませんが、一般的には「数回の使用が限界」とされています。製品や使用環境によって大きく異なるため、一概に「〇回使える」とは言い切れません。しかし、平均的な使用回数の目安としては、2~5回程度と考えられています。
布製タイヤチェーンの寿命は、主に以下の3つの要因によって変わります。
- 走行距離と路面の状態
布製タイヤチェーンは雪道での使用を前提に設計されています。そのため、乾燥したアスファルトや凍結していない道路を走行すると、摩耗が急激に進み、1回の使用でも破損する可能性があります。特に、氷が張っていない圧雪路では比較的長持ちしますが、雪がない舗装路を長時間走行すると、わずか数キロでダメになってしまうこともあります。 - 速度と運転方法
布製タイヤチェーンを装着した状態では、推奨される最高速度が約30~50km/hとされていることが多いです。これを超える速度で走行すると、摩耗が早まり、布の繊維がほつれる原因となります。また、急加速や急ブレーキを繰り返す運転も、タイヤチェーンの劣化を早める要因です。特に、カーブを曲がる際や坂道の登り降りでは慎重な運転が求められます。 - 製品の品質とメンテナンス
布製タイヤチェーンは各メーカーによって品質が異なります。高品質な製品ほど耐久性が高く、数回の使用に耐えられるものもあります。一方で、安価な製品や非正規品は、1回の使用でも損傷することがあります。また、使用後のメンテナンスも重要で、水分をよく拭き取り、乾燥させてから保管することで、次回の使用時の劣化を抑えられます。
このように、布製タイヤチェーンの使用回数は「使用環境」「運転方法」「製品の品質」に大きく左右されます。適切に使えば複数回使用できますが、誤った使い方をすると、1回で使えなくなることもあるため、注意が必要です。
オートソックは何回使える?寿命の目安
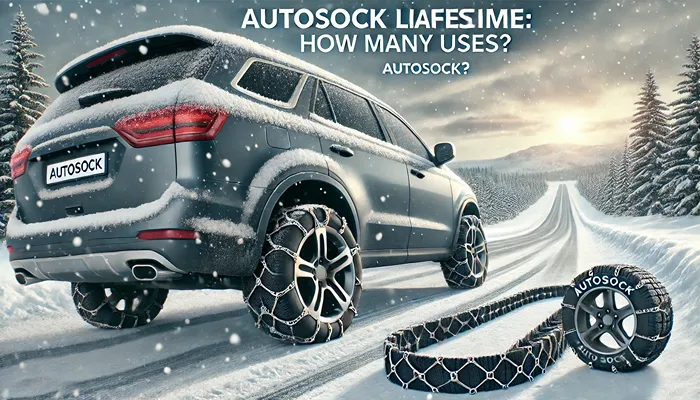
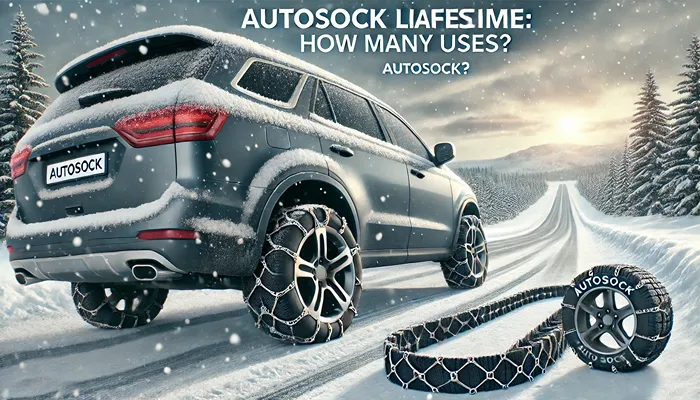
オートソックは、布製タイヤチェーンの代表的なブランドであり、世界的にも広く使用されています。その最大の特徴は、簡単に装着できることと、雪道での高いグリップ力です。しかし、オートソックも他の布製タイヤチェーンと同様に、耐久性には限界があります。
オートソックの公式情報によると、使用回数の目安は「10回前後」とされています。ただし、この回数はあくまで参考値であり、使用環境や運転方法によって大きく異なります。例えば、以下のような条件によって寿命が短くなる可能性があります。
- 乾燥した舗装路を走行した場合
オートソックは雪道や氷上での使用を前提に作られています。乾燥したアスファルトを長時間走行すると、摩耗が激しくなり、1回の使用でも破損することがあります。そのため、雪道を抜けたらすぐに外すことが推奨されています。 - 高速度で走行した場合
オートソックの推奨速度は最大50km/h程度です。それ以上の速度で走行すると、布の繊維が削れたり、破れたりするリスクが高くなります。特に高速道路での長時間走行は寿命を大幅に縮める原因になります。 - 急加速・急ブレーキを繰り返した場合
乱暴な運転をすると、オートソックにかかる負荷が大きくなり、摩耗が早まります。特に、急発進や急ブレーキを繰り返すと、布の繊維がほつれたり、穴が開いたりすることがあります。 - 使用後のメンテナンスを怠った場合
使用後に濡れたまま放置すると、オートソックの繊維が傷みやすくなり、次回使用時に強度が落ちてしまいます。水分をよく拭き取り、乾燥させてから保管することで、寿命を延ばせます。
このように、オートソックの寿命は「適切な使い方」をすれば比較的長く使えますが、誤った使用をすると数回で使えなくなることもあります。長持ちさせるためには、雪道以外での使用を避け、速度を守り、適切なメンテナンスを行うことが重要です。
布チェーンはノーマルタイヤでも使えるのか?


布製タイヤチェーンは、基本的にノーマルタイヤ(スタッドレスではない一般的なタイヤ)にも使用できます。しかし、いくつかの注意点があるため、適切な使い方を理解しておくことが重要です。
まず、布チェーンは主に「一時的な滑り止め」として設計されています。そのため、スタッドレスタイヤの代替品として長期間使用するものではなく、突然の降雪や急な積雪に備えるための補助アイテムと考えるのが適切です。ノーマルタイヤに装着することで、雪道やアイスバーンでも一定のグリップ力を得ることができますが、スタッドレスタイヤほどの安定性は期待できません。
また、ノーマルタイヤに布製チェーンを装着する場合、以下の点に注意が必要です。
- 乾燥した路面での使用はNG
布製タイヤチェーンは雪道や凍結路面での使用を前提に作られています。乾燥したアスファルトの上を走ると摩耗が激しくなり、耐久性が著しく低下してしまいます。そのため、雪道を抜けたらすぐに取り外すことが推奨されています。 - チェーン規制には適合しない場合がある
一部の地域では、積雪時に「チェーン装着が義務付けられる道路」があります。しかし、布チェーンは法律上の「チェーン」と見なされない場合があり、規制対象の道路では使用できないことがあります。事前に道路交通法や各自治体のルールを確認しておくと安心です。 - 過信は禁物
ノーマルタイヤに布チェーンを装着すれば、ある程度のグリップ力は得られますが、急な坂道やアイスバーンではスタッドレスや金属チェーンに比べて滑りやすくなります。過信せず、安全運転を心がけることが大切です。 - 使用回数に制限がある
布製チェーンは消耗品であり、数回使用すると劣化します。特にノーマルタイヤに装着する場合、トレッドパターン(溝)の影響で摩耗が早まることがあるため、定期的に状態を確認し、ダメージがある場合は交換が必要です。
結論として、布製タイヤチェーンはノーマルタイヤにも使用可能ですが、あくまで「緊急時の対策」として考え、長期的な使用や過酷な雪道での走行には向いていません。適切な場面で使用し、必要に応じてスタッドレスタイヤや金属チェーンとの併用を検討することが大切です。
タイヤチェーンの耐久性はどのくらい?


タイヤチェーンの耐久性は、材質や使用環境によって大きく異なります。一般的には、金属チェーン、非金属チェーン、布製チェーンの3種類があり、それぞれ寿命の目安が異なります。
1. 金属チェーンの耐久性
金属製のタイヤチェーンは、最も耐久性が高いとされています。特に、スチールや合金製のチェーンは、適切に使用すれば数十回以上の使用に耐えられます。ただし、使用する環境によって寿命は大きく変わります。
- 雪道や氷上での使用が前提
- 乾燥路面を走ると摩耗が急速に進む
- 走行時の振動や音が大きいため、快適性には欠ける
また、金属チェーンはサビやすいため、使用後のメンテナンスが重要です。しっかりと乾燥させて保管すれば、より長く使うことができます。
2. 非金属チェーンの耐久性
非金属チェーン(ゴムやプラスチック製)は、金属チェーンよりも柔軟性があり、走行時の振動が少ないのが特徴です。耐久性は金属チェーンに比べると劣るものの、5~10回程度の使用が可能とされています。
- ゴム製のものは弾力性があり、亀裂が入ると劣化が早まる
- プラスチック製は軽量だが、衝撃に弱い
- 気温の変化によって硬くなり、割れる可能性がある
非金属チェーンは比較的装着が簡単で、乗り心地が良い反面、長期間の使用には向いていません。
3. 布製チェーンの耐久性
布製タイヤチェーンは、軽量で取り付けが容易な反面、耐久性には限界があります。一般的な使用回数の目安は2~5回程度です。
- 雪道では一定のグリップ力を発揮する
- 乾燥した舗装路ではすぐに摩耗してしまう
- 過度なスピードや急加速・急ブレーキで寿命が短くなる
布製チェーンは、突然の雪道に対応するための「緊急用」として考え、長期間の使用には向いていないことを理解しておく必要があります。
結論として、タイヤチェーンの耐久性は「材質」「使用環境」「メンテナンス」によって大きく左右されます。長持ちさせるためには、適切な場面で使用し、不要なときは速やかに取り外すことが大切です。
布製タイヤチェーンのデメリットと注意点
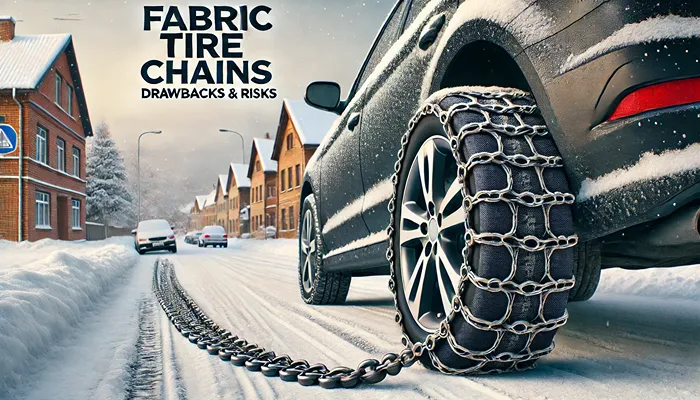
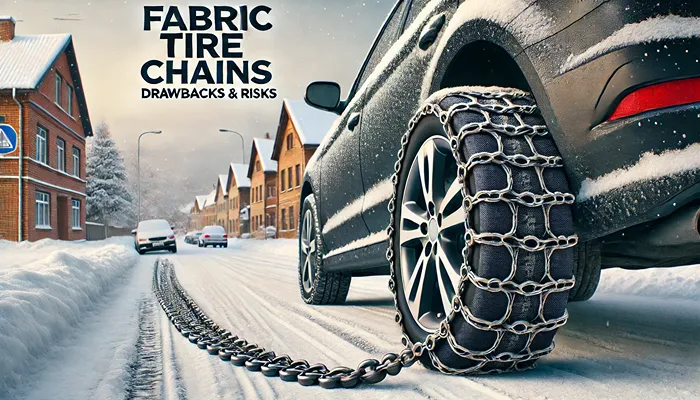
布製タイヤチェーンには多くのメリットがありますが、一方でデメリットや注意すべき点も存在します。特に、耐久性の問題や使用環境の制限などを理解しておかないと、適切に活用できません。
1. 耐久性が低い
布製タイヤチェーンの最大のデメリットは、その耐久性の低さです。金属チェーンや非金属チェーンに比べて摩耗が早く、数回の使用で使えなくなることがあります。特に、以下の状況では寿命が著しく短くなります。
- 乾燥したアスファルトを走行した場合
雪道専用のため、雪がない舗装路を走ると急速に摩耗し、1回の使用で破れることもあります。 - 急加速や急ブレーキを繰り返した場合
摩擦が大きくなり、布が破れたりほつれたりする原因になります。
2. 法律上の「チェーン規制」に適合しないことがある
一部の道路では、積雪時に「チェーン装着が義務付けられること」があります。しかし、布製タイヤチェーンは「チェーン」として認められないケースがあり、規制対象の道路では使用できないことがあります。事前に規制の内容を確認しておくことが重要です。
3. 長距離走行には向いていない
布製チェーンは「一時的な滑り止め」としては有効ですが、長距離走行には向いていません。長時間の使用では布が摩耗し、グリップ力が低下するため、途中で交換が必要になることもあります。
これらのデメリットを理解した上で、布製タイヤチェーンは「緊急時の補助アイテム」として使うのが適切です。適切な状況で使用し、不要な場合は速やかに取り外すことで、安全かつ効果的に活用できます。
布製タイヤチェーンは何回使える?劣化や寿命の確認方法


- タイヤチェーン未使用時の寿命はどのくらい?
- 非金属チェーンは未使用でも劣化する?
- タイヤチェーンの製造年を確認する方法
- オートソックが使えないケースとは?
- 非金属チェーンの劣化を防ぐための保管方法
- 長持ちさせるための使い方とメンテナンス方法
タイヤチェーン未使用時の寿命はどのくらい?
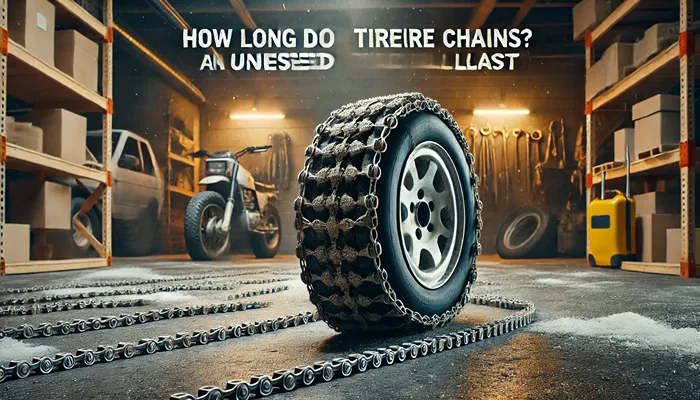
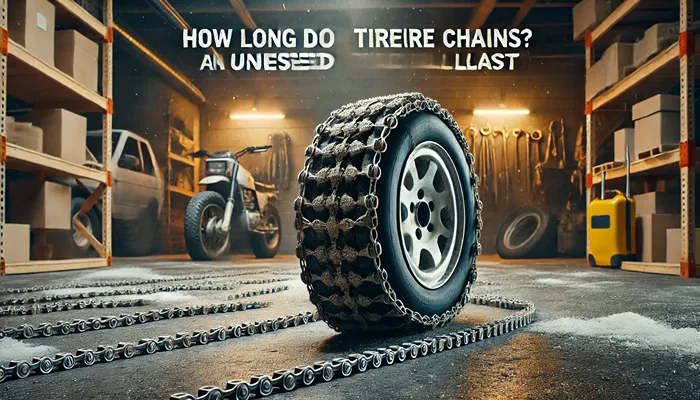
タイヤチェーンは未使用のまま保管していても、経年劣化によって寿命を迎えることがあります。特に、金属チェーン・非金属チェーン・布製チェーンではそれぞれ劣化のスピードが異なるため、適切な保管方法と定期的なチェックが重要です。
1. 金属チェーンの未使用時の寿命
金属チェーンは基本的に耐久性が高く、未使用であれば10年以上使用可能な場合もあります。ただし、保管環境が悪いと以下のような問題が発生することがあります。
- 錆びによる劣化
湿気が多い場所に長期間放置すると、金属部分が錆びてしまい、強度が低下します。特に、海沿いや湿度の高い倉庫などでは錆びやすいため、定期的に状態を確認する必要があります。 - 可動部分の固着
チェーンのジョイント部分が動かなくなることがあります。保管時には防錆スプレーを吹きかけておくと、スムーズな動作を維持しやすくなります。
2. 非金属チェーンの未使用時の寿命
非金属チェーン(ゴム・ウレタン・樹脂製)は、未使用であっても5~7年程度が寿命の目安とされています。これは、経年劣化によって素材が硬化し、ひび割れが発生するためです。
- ゴム製のチェーンは、紫外線や温度変化によって弾力性が失われ、ひび割れしやすくなります。
- 樹脂製やウレタン製のチェーンも、時間とともに硬化し、割れやすくなるため、未使用であっても古いものは交換が必要です。
3. 布製チェーンの未使用時の寿命
布製チェーンは最も寿命が短く、未使用でも3~5年程度が限界とされています。これは、素材自体が湿気やカビ、紫外線によって劣化しやすいためです。
- 保管時に湿気を吸収するとカビや繊維の劣化が進む
- 長期間放置すると繊維が脆くなり、耐久性が低下する
未使用でも定期的に取り出して状態を確認し、異常があれば早めに交換を検討することが大切です。
未使用時の寿命を延ばすためのポイント
- 乾燥した場所で保管する(湿気や直射日光を避ける)
- 定期的に状態をチェックする(劣化がないか確認する)
- 防錆スプレーやシリコンスプレーを活用する(金属チェーンやゴムチェーンの場合)
未使用のタイヤチェーンであっても、経年劣化は避けられません。特に、長期間保管していたものを使用する場合は、事前に状態を確認し、安全に使えるかどうかをチェックしておきましょう。
非金属チェーンは未使用でも劣化する?


非金属チェーンは未使用であっても劣化することがあります。金属チェーンと違い、ゴムやウレタン、樹脂といった素材は経年劣化しやすいため、使用しなくても状態を定期的に確認することが重要です。
1. ゴム製チェーンの劣化
ゴム製の非金属チェーンは、時間の経過とともに弾力性が失われ、硬化やひび割れが発生しやすくなります。特に、以下の環境で保管すると劣化が進みやすくなります。
- 直射日光が当たる場所(紫外線による劣化)
- 湿度が高い場所(カビや腐食の原因)
- 寒暖差が激しい環境(ゴムの硬化が進む)
2. 樹脂製・ウレタン製チェーンの劣化
樹脂やウレタン製のチェーンも、長期間保管すると硬化や割れが発生する可能性があります。特に、使用頻度が低い場合、素材自体が劣化してしまい、いざ使用しようとしたときに破損することがあります。
- 気温変化による影響:寒冷地ではウレタンが硬くなり、割れやすくなる
- 保管方法による影響:湿気が多いと素材が脆くなる
3. 未使用でも劣化を防ぐためのポイント
- 直射日光を避け、風通しの良い場所に保管する
- シーズン前に劣化の有無を確認する
- ゴム製の場合はシリコンスプレーを塗布して保護する
未使用だからといって油断せず、定期的に点検し、必要に応じて新しいものに交換することが重要です。
タイヤチェーンの製造年を確認する方法


タイヤチェーンの製造年を確認する方法はいくつかありますが、メーカーごとに表示方法が異なるため、正しい方法でチェックする必要があります。特に、金属チェーン・非金属チェーン・布製チェーンでは確認の仕方が異なります。
1. 金属チェーンの製造年の確認方法
金属製タイヤチェーンの場合、多くのメーカーではパッケージや説明書に記載されています。また、一部の高品質な製品では、チェーン本体に刻印があることもあります。
- パッケージに記載(例:「製造年月:2022年10月」など)
- 説明書に記載(型番と共に製造年が明記されている)
- 本体に刻印(メーカーによって異なるが、チェーンのジョイント部などに刻印があることも)
2. 非金属チェーンの製造年の確認方法
非金属チェーン(ゴム・ウレタン・樹脂製)の場合、製造年月が本体またはタグ部分に記載されていることが多いです。
- タグやラベルに記載されている(例:「2023/05」など)
- 型番からメーカーのサイトで製造年を確認できる場合がある
- 説明書やパッケージに記載されていることが多い
3. 布製チェーンの製造年の確認方法
布製チェーンの場合は、パッケージや説明書に製造年月が記載されていることが一般的です。また、一部のメーカーでは、布地に小さなタグが縫い付けられており、そこに製造年月が書かれていることがあります。
- パッケージや説明書に記載
- 布製品の内側にタグがある場合、そこに記載
- メーカーに型番を伝えて製造年を確認することも可能
製造年を確認する理由
タイヤチェーンは、未使用であっても経年劣化するため、古いものは安全性に問題がある可能性があります。特に、5年以上経過している場合は、ひび割れや劣化が進んでいないか確認することが大切です。
製造年をチェックし、古くなっている場合は早めに交換を検討することで、雪道でも安全に走行できるようになります。
オートソックが使えないケースとは?


オートソックは簡単に装着でき、雪道でも高いグリップ力を発揮する布製タイヤチェーンですが、すべての状況で使用できるわけではありません。特定の道路環境や車両条件によってはオートソックが使えないケースがあるため、事前に確認しておくことが重要です。
1. 乾燥路面での走行
オートソックは雪道や凍結路面での使用を前提とした製品のため、乾燥した路面では摩擦による劣化が激しくなります。特に、以下の状況では使用を避けたほうがよいでしょう。
- アスファルトやコンクリートが露出している道路
雪が部分的に残っている程度の道路では、オートソックの繊維が急激に摩耗し、数キロ走行するだけで使えなくなることがあります。 - 駐車場や市街地など除雪が行き届いた場所
除雪が完了している道路では、オートソックの寿命が著しく短くなるため、早めに取り外す必要があります。
2. 急勾配の坂道や深雪
オートソックは雪道や凍結路面でのグリップ力を高めるものの、金属チェーンのような食い込み性能はありません。そのため、以下のような状況では十分な効果を発揮できない可能性があります。
- 急な上り坂や下り坂
特に、積雪が深く圧雪されていない急勾配の坂道では、スリップすることがあります。 - 30cm以上の深雪
オートソックは雪の表面をグリップする構造のため、深雪ではタイヤが埋まってしまい、走行困難になる場合があります。
3. チェーン規制の「装着義務区間」での使用
日本では、大雪時に「チェーン装着義務区間」が指定されることがあります。この場合、オートソックはチェーン規制を満たさないため、装着していても通行が認められないことがあります。
- 国土交通省が定める「金属チェーン必須」の道路
一部の峠道や高速道路では、布製チェーンや非金属チェーンでは通行が許可されないことがあります。
事前に規制内容を確認し、必要に応じて金属チェーンを準備しておくと安心です。
4. 特定の車両での使用不可
オートソックはすべての車両に適合するわけではなく、以下のようなケースでは使用が推奨されていません。
- 特殊なタイヤサイズの車両(サイズが適合しない場合)
- 重量のある車両(トラックやSUVの一部)
一部の大型車両では、オートソックの耐久性が不足し、すぐに破れる可能性があります。
オートソックを安全に使用するためには、事前に適合サイズを確認し、走行条件に注意することが大切です。
非金属チェーンの劣化を防ぐための保管方法


非金属チェーンはゴム・ウレタン・樹脂などの素材で作られているため、適切に保管しないと劣化が進みやすいという特徴があります。長く使用するためには、保管環境や方法に注意することが大切です。
1. 直射日光を避ける
非金属チェーンは紫外線に弱いため、日光が当たる場所に放置すると素材が劣化してしまいます。特に、以下のような状況は避けるべきです。
- 屋外での保管(紫外線で硬化・変色する)
- 窓際や車内(温度上昇による影響)
紫外線対策として、専用ケースに入れて保管するのが理想的です。
2. 湿気を防ぐ
ゴムや樹脂製のチェーンは湿気の影響を受けやすいため、湿気がこもる場所での保管はNGです。以下のようなポイントに注意しましょう。
- ビニール袋に密閉しない(湿気がたまる)
- 乾燥剤を入れておくと効果的
- カビや腐食を防ぐため、風通しの良い場所に保管
3. 適切な温度で保管する
高温・低温にさらされると素材が劣化しやすくなるため、極端な温度変化がある場所は避けることが大切です。
- 真夏の車内は避ける(高温で変形することがある)
- 極寒の屋外倉庫は避ける(寒さでゴムが硬化する)
理想的な保管場所は、室内の温度変化が少ない場所です。
4. シーズンオフには状態をチェック
長期間保管する前に、ひび割れや損傷がないかチェックし、軽く拭き取ってから保管することで、次のシーズンでも安心して使うことができます。
正しい保管方法を実践することで、非金属チェーンの劣化を防ぎ、長く使い続けることができます。
長持ちさせるための使い方とメンテナンス方法
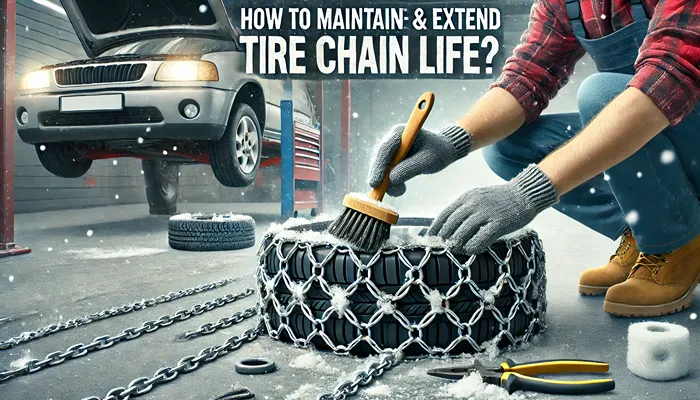
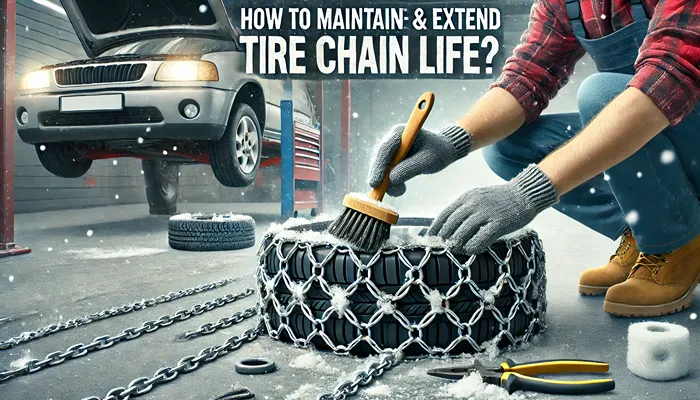
タイヤチェーンは適切な使い方とメンテナンスを行うことで、寿命を延ばし、安全に使用することが可能です。特に、非金属チェーンや布製チェーンは摩耗しやすいため、長持ちさせるための工夫が重要になります。
1. 走行前に装着状態を確認
- 正しく装着されているかチェック
緩んでいたり、ねじれていると摩耗が早まるため、装着後にしっかり確認することが大切です。 - 片側だけに負荷がかからないようにする
偏った装着をすると一部分だけが早く摩耗し、耐久性が低下してしまいます。
2. 乾燥路面では走行しない
タイヤチェーンは雪道や凍結路面で使用するものなので、アスファルトの上では急激に摩耗します。以下のような場合は、早めに取り外すことが重要です。
- 除雪された道路では外す
- 駐車場や一般道路に出る前にチェック
3. 使用後はしっかりメンテナンス
使用後のメンテナンスが不十分だと、次回使うときに劣化している可能性があります。
- 水洗いして汚れを落とす
- しっかり乾燥させる(湿気がこもらないようにする)
- 収納ケースに入れて保管する
4. 定期的に劣化をチェック
シーズンごとに以下の点を確認すると、安全に使い続けることができます。
- ゴムや布製のチェーンはひび割れがないか確認
- 金属チェーンは錆びていないかチェック
- 装着用のフックや固定具に異常がないか見る
こうしたメンテナンスを行うことで、タイヤチェーンを長持ちさせ、安全な雪道走行を実現できます。
【総括】タイヤ チェーン 布 何回使える?耐久性と使用時の注意点
- 布製タイヤチェーンはポリエステルなどの特殊繊維で作られている
- 軽量で装着が簡単なため、初心者にも扱いやすい
- 雪道でのグリップ力は高いが、耐久性には限界がある
- 一般的な使用回数の目安は2~5回程度
- オートソックは比較的耐久性が高く、10回前後使えることが多い
- 乾燥した路面では急激に摩耗し、1回で使えなくなることもある
- 急加速・急ブレーキを避けることで寿命を延ばせる
- ノーマルタイヤにも装着できるが、過信は禁物
- チェーン規制区間では使用不可の可能性がある
- 布製チェーンは長距離走行には向いていない
- 非金属チェーンも未使用でも劣化するため、定期的な確認が必要
- タイヤチェーンの製造年はパッケージやタグで確認できる
- 使用後は汚れを落とし、乾燥させて保管すると劣化しにくい
- 直射日光や湿気を避けた環境で保管するのが望ましい
- 正しい装着とメンテナンスで、少しでも長持ちさせることが可能






コメント